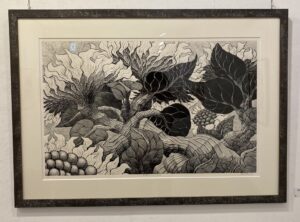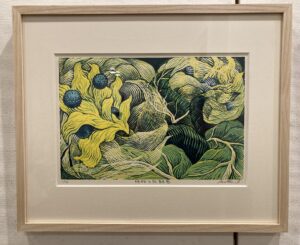風景画
小山剛さんにとってはメインテーマではないものの大切な画題。
人物画がメインであり、人物画に対しては「戦う」という意識がある。
真っ向勝負の厳しい気持ちの中で自分の絵に対してそう簡単にOKは出せない。考えに考え抜いたうえでの制作。ある意味手あかがいっぱいついた領域なのだそうです。
一方風景画は絵を描くことが好きだと意識し始めた中学生の頃から得意であり、教科書で知った遠近法など研究してうまくいったときの喜びはとても新鮮だったと言います。絵が上手だった子供の多くが経験することでもあるかもしれません。
メインである人物画を描いていてともすると重くなってしまう「絵を描くこと」
風景画を描くとあの頃の新鮮な気持ちが蘇るのだそうです。
そうするとまた人物画に対して新たな気持ちで取り組める。
小山さんにとってどちらも大切な領域ということです。
ここで1つ面白エピソード。
今回の個展の作品25点の中の1点に「prism」という文字が隠れています。
探し当てた方には何かほんのちょっといいことをプレゼントします。